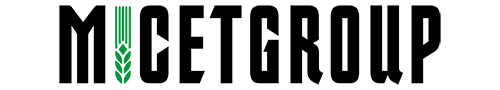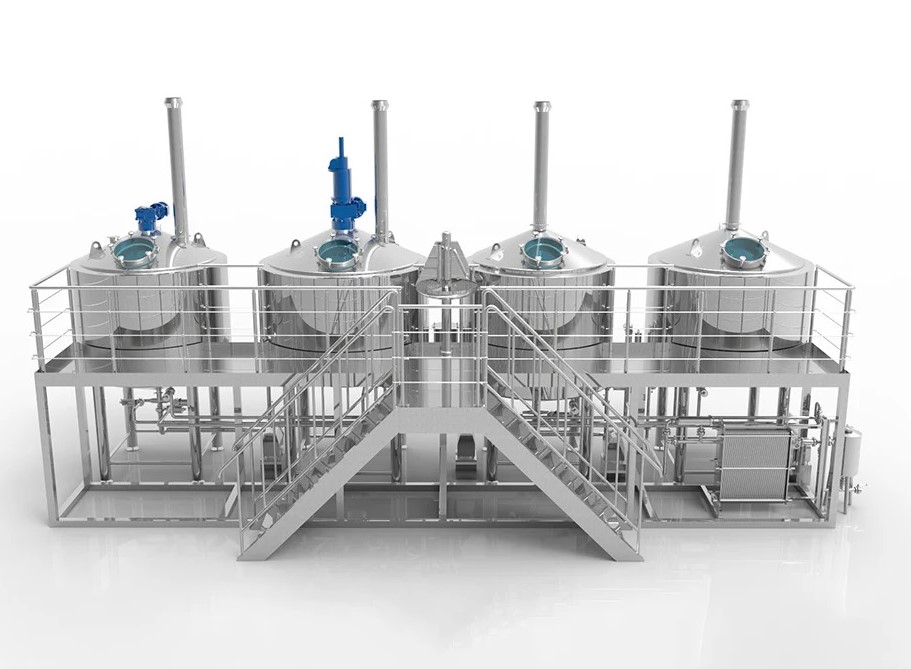醸造用酵母は生命力が強く、細胞壁も強いので、アルコールのある酸性の環境でも生き残ることができますが、特にビールの保存期間が長く、生存圧の強い発酵環境では死なないとは限りません。
酵母が死滅すると、酵母の自己分解によってビールに不快な風味が生じます。また、酵母が大量に沈殿すると、不快な口当たりや欠陥の原因となります。
概要
長い間、酵母の自己融解の原因は十分に研究されてこなかった。しかし長い研究の末、酵母の死は酵母自身の「最後のショー」とも言えることがわかった。酵母は死んだ後、蓄えていた栄養分を他の酵母に提供する。
酵母のオートファジーは、それ自身の作動メカニズムである。一部の酵母が重要でなくなったり、老化したりすると、他の酵母がこれらの老化した酵母細胞を分解する。これは、老化細胞を分解することによって、酵母自身のサイクルを作り出し、それによって内部の栄養素を再び放出する。
酵母の自己分解がビールに及ぼす影響
酵母細胞の死と自己分解は正常な現象である。酵母が自己分解する理由は、細胞内に酵素を持っており、死後、細胞内構造と細胞膜を分解し、最終的に細胞内容物といくつかの分解生成物が損傷した細胞膜を通してビール中に浸透するためである。
特に短鎖脂肪酸やアミノ酸は、イースト臭やカビ臭といった不快な臭いの原因となる。また、脂肪酸は分解すると石鹸のような臭いがする。同時に、細胞膜上の高分子物質もビールの濁りの原因となる。
また、自己分解した酵母が放出するアミノ酸やヌクレオチドは、ビールに肉や硫黄のような不快な苦味を与える。自己分解酵母の量が多い場合、これらの物質はビールのpHを著しく上昇させ、味をさらに変化させる。
ビールの泡の安定性に影響を与える。二次発酵させたビールを瓶詰めする際、複雑な非発酵性糖類が酵素によって単純な発酵性糖類に分解され、他の生きた酵母によって消費され、過炭酸やその他の問題を引き起こす。
さらに、これらの自己溶解物は、細菌汚染に適した栄養環境も提供する。
まとめると、酵母の自己分解による悪影響は以下の通りである:
- ヘッドフォームの安定性が悪くなり、泡がすぐに消えてしまう
- 風味の欠陥:イースト、肉、かび臭い、クレオソート、石鹸の香りなど
- pH上昇
- 細菌汚染のリスクを高める
- ビールの色が変わる
- 濁り、ろ過が難しくなる
- ビールの味の安定性の低下
- ジアセチル含有量の増加(還元不足が原因)
- 苦味が長引く
酵母の自己融解を防ぐ/減らすための対策
健康的な酵母を選ぶ
健康で活力のある酵母を使用する(活力とは酵母が生きているかどうかという意味ではなく、酵母が活動しているかどうかという意味である)。
健全な酵母集団の鍵は、若く元気な酵母集団の基盤である。酵母は栄養分に富み、酸素が供給されると酵母増殖期(指数関数的成長)に入る。
酵母の生存圧を高め、自己分解の可能性を促進することに加え、酵母の過剰なリサイクルや再利用は、乳酸菌や他の野生酵母による汚染の可能性も高める。
発酵条件コントロール
高い発酵温度(特に26℃以上)や急激な温度変化は避ける。また、糖分が高すぎる麦汁に直接酵母を接種すると、酵母が浸透圧ショックにさらされる。
主発酵後、樽を注ぐ(自家製ビール)/イーストを漕ぐ(商業用ビール)で間に合います。イーストの沈殿物を発酵タンクに長時間放置しておくと、イーストの自己分解によってビールに風味の欠陥が生じる原因にもなります。イースト入りの発酵槽は、高温で発酵するエールでは約2週間、低温で貯蔵するラガーではもう少し長持ちする。
酵母の活性に影響を与える要因は、アルコール度数、栄養分、発酵槽の圧力である。また、酵母株によってアルコール、炭酸ガス、酸に対する感受性が異なるため、酵母株の種類に応じて対応する発酵条件をコントロールする必要がある。
缶詰を作る際の対策
酵母の自己融解をできるだけ避けるため、缶詰の際にはビールを酵母の沈殿物にできるだけ入れないようにする。二次発酵の炭酸を満たすには、ビール1mlあたり約0.5~1億個の酵母があれば十分ですが、そうでない場合は新しい酵母を加えます。
主発酵が終わった後、タンクに入る酵母の量を減らすために、何らかの物理的分離方法(濾過や長期の低温沈殿など)を使うことができる。しかし理論的には、ほとんど透明なビールでも炭化するのに十分な酵母が存在する。
結論
酵母の自己分解は避けられないが、耐圧性の強い酵母を使い、保存温度を下げることで遅らせることができる。同時に、最終タンク内の酵母量が少なければ、味への影響も最小限に抑えられる。